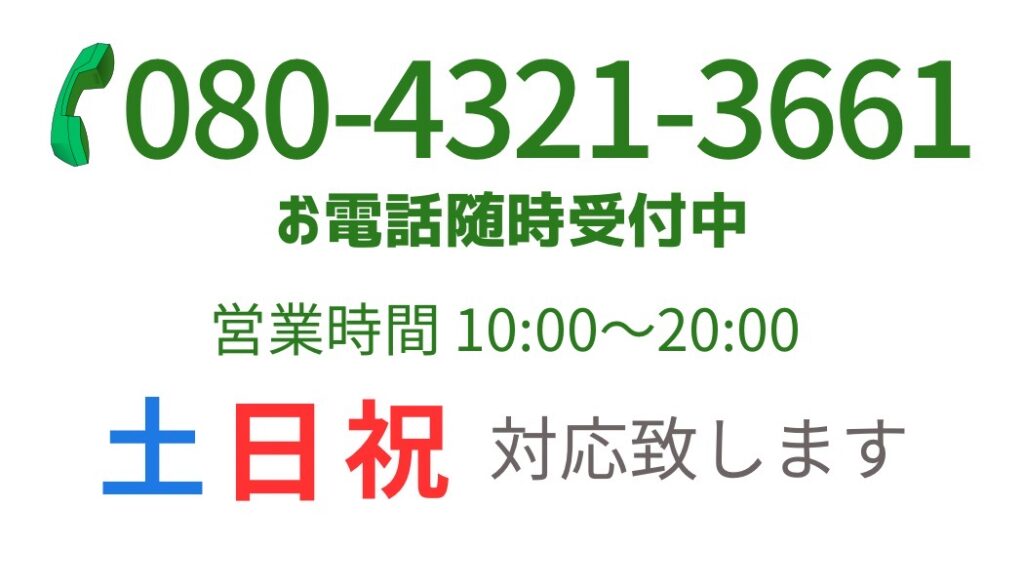定住者ビザ
Long-term Resident VISA
定住者ビザ
定住者ビザは法務大臣が「特別な理由」を考慮して、一定の在留期限を決めて日本に居住を認めた者に対して与えられるビザです。そのため、さまざまなバック・グラウンドや家族関係の事情をもった方に対して多く与えられています。
定住者は身分系のビザで、活動に制限がありません。ただし、在留期限はあります。
定住者ビザには大きく分けて2つのタイプがあります。
ひとつは「定住者告示」といい、あらかじめ定められた典型的なケースに当てはまる場合です。
もう一つは「告示外定住」といい、定住者告示に定められていないケースに該当する外国人に対して、個々に在留の許可不許可の判断を法務大臣が下します。
定住者告示→予め定められている典型的な定住者のケース
告示外定住→典型的な定住者のケースに該当しない外国人で、個々に在留の許可不許可を判断
定住者告示
定住者告示をもってあらかじめ定められるカテゴリーは以下のとおりとなっています。
定住者告示①~⑧の対象となる外国人の方
- タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの
- イ)日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子
- ロ)この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの
- 削除
- 日本人の子として出生した者の実子(②または⑧に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
- 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(③または⑧に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
- 次のいずれかに該当する者(①~④または⑧に該当する者を除く。)に係るもの
- イ)日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
- ロ)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(③または④に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
- ハ)③または④に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの
- 次のいずれかに該当する者(①~④または⑧に該当する者を除く。)に係るもの
- イ)日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
- ロ)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(③④又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
- ハ)③④または前号ハ)に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
- ニ)日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
- 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(①~④、⑥または⑧に該当する者を除く。)に係るもの
- イ)日本人
- ロ)永住者の在留資格を持って在留する者
- ハ)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
- ニ)特別永住者
- 次のいずれかに該当する者に係るもの
- イ)中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
- ロ)前記イ)を両親として昭和20年9月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
- ハ)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する者
- ニ)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって同条第4項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
- a)配偶者
- b)20歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
- c)日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
- d)実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(55歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
- e)dに規定する者の配偶者
- ホ)6歳に達する前から引き続き前記イ)からハ)までのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子
素行善良要件
定住者告示の3号・4号・5号ハ・6号ハでは次の素行善良要件を満たすことが求められます。
素行善良要件
次のいずれにも該当しないことが求められます。
- 日本国または外国の法令に違反して、懲役や禁錮罰金などこれらに相当する刑に処せられたことがある
- 少年法の保護処分が継続中の者(少年法第24条第1項第1号および第3号)
- 日常や社会生活で違法行為や風紀を乱す行動をくり返し行うなど素行善良と認められない特段の事情がある場合
- 他人に入管法で定める証明書の交付または許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者、不法就労のあっせんを行った者
告示外定住者
典型的な定住者ビザに該当しないケースの告示外定住者ですが、前例が蓄積されていくにつれて、こちらもある程度のカテゴリーが発生してきています。告示外定住者は大きく分けて以下のカテゴリーとなります。
告示外定住の主なカテゴリー
離婚定住
日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザで在留していた方が、離婚した場合に付与されうる定住のカテゴリーです。要件としては、通常の夫婦として家庭生活を実体的に営んでいたということが必要です。つまり、夫婦として相互扶助や交流がしっかりと継続して存在していたこと、加えて離婚にいたるいきさつなどを詳細に証明する必要があります。DVなどの事実があれば、認められる可能性も高くなります。
死別定住
こちらも日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザで在留していた方の配偶者が亡くなられた場合に、付与されうる定住のカテゴリーです。
日本人の実子を育てるための定住
日本人とのあいだに生まれた実子を監護・養育する外国人の方に付与されうる定住のカテゴリーのひとつです。子どもが生まれた時点で夫か妻かが日本国籍を有していることが主な要件となります。その他生計を営める資産又は技能があること。子どもの親権をもっていること。実際にある程度、子どもを養育していること。などが求められます。入管による詳細な実態調査や事情聴取も行われます。
婚姻破綻定住
婚姻関係が事実上破綻しており、婚姻はいまだ続いているものの夫婦の双方に婚姻を継続する意思がなくなり、同居やお互いの協力扶助が行われなくなった状態の固定化が認められ、将来的に婚姻関係を修復・維持しうる可能性がなくなった場合の外国人に付与されうる定住のカテゴリーのひとつです。
仮に、いまだ婚姻が破綻していると認められない場合には日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザを更新することを検討してみましょう。